日本経済国際共同研究センター第1回国際コンファレンス
第1部 東南アジア金融危機の現状-その教訓
第1セッション:個別国の経験
韓国と東南アジアの通貨危機
- 報告者: Chi-Young Song (Kookmin University)
- 討論者: 深川由起子(青山学院大学)
この報告では、1997年にタイを皮切りとして生じた東南アジアの通貨危機のプロセスを、「伝染効果」に関する統計的な分析を交えて議論した。東南アジアの危機はそれぞれの国内金融制度が抱える脆弱性による部分が多いが、同時に急激な国際資本移動によって惹起された部分もある。IMFの政策は国際資本移動がもたらす撹乱効果に十分に対処できていないという点で、再検討に値する。
インドネシアの金融制度と金融危機
- 報告者: Iwan J. Azis (Cornell University and University of Indonesia)
- 討論者: 高阪章(大阪大学)
この報告では、インドネシアの経済発展戦略が必ずしも健全な銀行制度に立脚することなく進められたこと、そのために銀行部門と企業部門の間に非効率的取引関係が形成されがちであったことを指摘し、金融システムの制度改革の手順として、国内の銀行、金融機関の健全化が金融自由化に優先されるべきであると主張する。
タイの金融部門が抱える問題点と対応策
- 報告者: Khun Aswin Kongsiri (The Bangkok Bank of Commerce)
- 討論者: 奥田英信(一橋大学)
報告者はタイの政府系金融機関から破綻した商業銀行の建て直しのために派遣された人物である。その実務的な経験から、マクロ経済運営と銀行に対する健全経営規制の組合せが、安定的な経済発展のためにきわめて重要であることを強調した。
第2セッション:金融危機のマクロ経済的、および制度的側面
1990年代の日本経済の不振と為替レート
- 報告者:Ronald McKinnon (Stanford University)
大野健一 (大学院政策科学研究科教授) - 討論者: 堀内昭義(東京大学)
この報告は日本の経済的不振が、絶えず円レートが上昇し続けるという期待を生み出した為替管理政策に由来していると主張する。日本の政府が取るべき政策は、為替レート円高の基調を変化させるために、円・ドルレートの安定化を目指すことであるとしている。人々が円高の長期的期待を抱かなければ、国際間の裁定取引の結果として日本の国内金利は上昇し、結果として国内のさらなる金融緩和政策が可能となる。
東南アジア経済は制度的な転換点を迎えているか
- 報告者: 青木昌彦(Stanford University and MITI)
- 討論者: 堀内昭義 (東京大学)
この報告は、比較制度分析の視点から、日本を含む東南アジアの経済・金融システムの構造を理論的に分析し、その今後の制度的変容を考察した。東南アジアの経済制度は純粋な市場メカニズムとは違った形で発展してきた。次第に市場競争の影響を受けるものの、今後も相対取引のもつ重要性が大幅に低下することはないであろうと報告者は予想する。市場競争は重要ではあるが、広い意味での制度の一部に過ぎないと言うのが報告者の基本的なスタンスである。
第3セッション:パネルディスカッション
現下の金融危機から得られる教訓
- 報告者: 伊藤隆敏 (一橋大学 東京大学)
- 討論者: Ronald McKinnon (Stanford University)
石見徹 (東京大学) - 司会: 堀内昭義 (東京大学)
このパネル・ディスカッションでは伊藤隆敏氏が近年の日本の銀行危機の展開と、政府による対策を展望した。次いでマッキノン教授が国際金融市場の動向という視点から、日本経済の動向が東南アジア経済に及ぼす影響を分析した。伊藤教授は日本の経済対策として、早急な不良債権処理を進める一方で、金融政策ではなく適度な財政政策に重点を置いた政策を提唱したのに対し、マッキノン教授は為替レートの安定化を目指す協調の必要性を強調した。両者のプレゼンテーションの後、フロワーからの質疑応答を含め、活発な議論が展開された。
(議事要約 堀内昭義)
第2部:市場経済における政府の役割の新しい方向性
競争入札における技術革新とその活用
- 報告者: Paul Milgrom (Department of Economics, Stanford University)
- 討論者: John McMillan
(Graduate School of International Relationsand Pacific Studies, University of California, San Diego)
Paul Milgrom教授:
ミルグロム教授がスタンフォード大学の同僚のロバート・ウィルソン教授と一緒に考案したAscending Bid Auctionが、アメリカにおける電波の利用権の競争入札において用いられ、大きな成功をおさめた。電波の利用権の入札においてニュージーランド及びオーストラリア政府が用いた方式は一般に失敗であったと思われている。ミルグロム教授はそれらの方式の問題点を簡単に指摘した後に、彼らの考案したAscending Bid Auctionが、それらの欠点を修正して、望ましい結果をもたらしたことを解説した。また、この入札方式はインターネットとパーソナルコンピュータの発展によって技術的に可能になった。ミルグロム教授のグループは、様々な入札に適用可能なコンピュータ・プログラムを開発しており、それらのプログラムがどのようなパフォーマンスを示すかをコンピュータ・シミュレーションによって分析している。このプログラムは、電波の入札だけでなく、電力関係の入札や住宅の入札にも用いられている。
John McMillan教授:
電波の利用権の入札において新しい入札方式が用いられて大きな成功をおさめたことは、セッションのテーマである「市場経済における政府の役割」に関して一つの新しい方向性を示している。電波の利用についてはその所有権を民間企業に売却してしまって、完全に市場経済に任せるという方策もありうる。しかし、電波の利用について、帯域間及び地域間で補完性が存在しているので、そのようなアプローチは必ずしも望ましい資源配分をもたらさない。電波の所有権がいったん分散してしまうと、それらをまとめることには大きな取引費用がかかってしまうからである。このような場合に望ましい結果をもたらす入札方式がascending bid auctionであり、この方式が考案されたことが市場経済を補完する政府の役割に新しい可能性を与えることになった。
市場経済の育成:所有権と金融
- 報告者: John McMillan
(Graduate School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego) - 討論者:藤原(奥野)正寛 (東京大学)
John McMillan教授:
社会主義経済から市場経済への移行を例にとって、市場経済の健全な機能のために果たすべき政府の役割について論じる。社会主義経済から市場経済への移行の際には、市場が存在していないことと企業の生産性が低いことが問題である。このような状態における政府の役割はそれほど簡単でない。
第一に、公営企業を民営化することは必ずしも良い結果をもたらすとは言えない。中国やベトナムでは民営化しなかったがめざましい経済発展が起きた。これに対して、ロシアでは民営化したにもかかわらず企業経営には改善が見られなかった。中国の成功は、企業に対して利潤の一部を与えるようにしたことと、2重価格制を採用したことが成功の要因である。
第二に、公営企業の民営化よりも新しい企業の参入の方が重要であるし、社会主義経済からの移行国の多くでは極めて速いスピードで新しい企業が参入してきた。新規参入は、・社会主義経済で不足していた消費財の生産を増加させる、・雇用を増加させる、・貯蓄を増加させ投資を促進する、・これまでの公営企業に対して競争をもたらし、公営企業の効率化にも貢献する、といった効果を持った。
世界銀行は「契約を有効にする法制度が市場経済の発展のために不可欠である」と主張したことがある。しかし、法制度が整備されていなくても、相手が契約を破ればそれ以降は取引をしないといったメカニズムや契約を破ったものには悪い評判が立ち他の取引相手との取引も困難になるといったメカニズムが機能する。社会主義経済から市場経済への移行においては、法制度が整備されていない国の方が、かえって良いパフォーマンスを示している。
また、金融システムの育成が市場経済の発展に不可欠であるという意見があるが、これも誤りである。ウクライナやロシアでは銀行ローンが多く供給されているがこれらの国のパフォーマンスは良くない。利潤の再投資や取引相手による信用供与が銀行融資の代替物として機能している。
市場経済の育成について最も害になると思われるのは、公務員やマフィアが市場取引において得られる利益を収奪することであり、これらを防止するシステムを作るのが政府の大きな役割である。
藤原(奥野)正寛教授:
(1)経済システムが補完的・代替的な様々な要素から成り立っている、(2)参入がダイナミズムの基礎にある、(3)法律や金融市場は暗黙の契約や利潤の再投入で代替できる、(4)政府の基本的な役割は収奪を防止することである、というMcMillan教授の主張は、移行国経済だけでなく発展途上国経済にも適用されるきわめて重要な指摘である。
しかし法制度がなくても、契約破りには評判などで制裁できるというが、教授が主張する経済のダイナミズムの原点である参入者は、評判を確立していないのではないか。また利潤の再投入は独占的な事業を前提する事になり、参入を制限しないだろうか。つまり、参入によるダイナミズムと、繰り返しゲームを基礎とした信頼による法制度の代替は、理論的には両立困難であり、より詳細な分析が必要だろう。
また移行国や途上国では、政府と既存事業者の結託によって参入制限やレント獲得活動が起こりがちである。収奪の防止は重要であり、結託の問題も含めて具体的な仕組みの分析が必要だろう。
(議事要約 金本良嗣)
第3部 自動車製造システム国際比較の新展開
日本の自動車生産システム:その受容・国際移転・進化
- 報告者: Frits Pil (University of Pittsburgh)
一次データに基づき、日本、アメリカ、ヨーロッパの自動車組立工場の生産性を自動車1台当たりの工数(人・時。ただし製品や工程の違いに関して補正済み)で測定した。また、組立工程に直接起因する出荷後不良率(台あたり外部不良率;J.D.パワー社データ)で、組立工場の製造品質を測定した。この結果、80年代末においては、日本企業の日本の工場は平均して欧米企業よりも、生産性、製造品質ともに高いことがわかった。また生産性と品質の間には正の相関がみられることが分かった。90年代前半の再調査によれば、日本企業と欧米企業の差はやや縮小したが依然残っている。興味深いことに、日系企業の米国現地工場の生産性・品質パフォーマンスは日本企業の日本工場と米国企業の米国工場の中間に位置した。また、日本企業の高パフォーマンスの背後には、ある製造能力のパターン(日本的なリーン生産方式)が観察されることがわかった。
そこで問題。いったい、こうした日本的な生産システムは、どの程度国際的に移転可能であるか?日本の多国籍自動車企業の直接投資にともなうシステム移転の状況を、米国現地工場の分析を通じて、日本的な慣行の移転可能性は、慣行のタイプによって異なることがわかった。また、環境の影響もさることながら、企業は環境を改変すること、また環境の影響をある程度遮断できることがわかった。
また、90年代においては、米国現地工場には日本方式がかなり現地向けに修正されて入ってきているにもかかわらず、結果としての生産性と製造品質は、日本に比べ遜色のないレベルに達していた。もっとも、日本の工場に比べて現地工場は取り扱う製品の種類が少ない、という点も勘案する必要がある。いずれにせよ、国際競争力のある慣行の国際移転にとって、国、文化、制度などは決定的な障壁にはならないことが明らかになったのである。
サプライヤーシステムの国際比較分析
- 報告者: Nazli Wasti (Middle East Technical University and University of Tokyo)
一次データに基づき、日米の自動車企業の購買(部分サプライヤー管理)慣行について、特に製品開発への部品企業の関与に着目しつつ比較分析した。一般に日本的な購買慣行とは、少数部品メーカーとのパートナー的関係、長期契約関係、早期で緊密なコミュニケーション、人的交流、共同問題解決・共同開発、等々の特徴を持つ。一方、旧来の米国方式は、敵対関係、短期指向、価格競争、多くの部品メーカーとの取引、自動車メーカーによる開発活動の独占、といった特徴を持つ。こうした差が、実際に日米間でみられるか、慣行の違いがパフォーマンスに影響するかをアメリカ174、日本122のサプライヤーに対するアンケート調査(1992年)で分析した。 回帰分析の結果、ほぼ仮説通り、日本的な「関係的契約法式」の場合は、よりカスタム化した部品、技術的不確実性の高い部品、戦略的重要性の高い部品である傾向があること、逆に競争は旧来型の方式のほうが激しいことなどがわかった。
また、開発活動への部品メーカーの関与は、サプライヤーによる部品設計の改善提案数が増えること、また製造性を重視した設計(Design for Manufacturing)が容易になることなどを通じて、実際に自動車の国際競争力アップに貢献することがわかった。
また、こうした日本的な慣行が、たとえばトルコのような新興自動車生産国のサプライヤーシステムに移転可能かどうかを、歴史や事例を通じて分析する必要がある。
製品開発システムの国際比較分析
- 報告者: 藤本隆宏 (東京大学教授)
1980年代における自動車企業の製品開発パフォーマンスを測定してみると、リードタイムや開発生産性などの指標では日本企業一般が平均して欧米企業に比べて高いパフォーマンスを示したが、他の指標、例えば総合商品力では、日本企業の中でも企業間のパフォーマンスの差が顕著であった。この結果、日本メーカーの中でもごく少数のみが、上記三つの指標全てで世界トップクラスの業績を残した。1980年代における自動車企業の製品開発組織能力(サプライヤー開発能力の活用、開発過程に埋め込まれた製造能力、サイマル・エンジニアリング遂行能力、技術者の幅広い専門能力、プロダクト・マネジャーの力量など)もまた、ある部分は地域特殊的、またある部分は企業特殊的であった。
1980年代後半から90年代前半にかけて、欧米の自動車メーカーは、日本車との国際競争を通じて、日本の高業績企業の製品開発能力をいわばベスト・プラクティスとして学習し、意識的・体系的に導入することによって、日本企業に対する逆キャッチアップを図った。この結果、特に米国自動車企業の製品開発パフォーマンスは、1990年代初頭までにリードタイムと開発生産性の両面で大幅に改善され、日本企業に対する部分的キャッチアップを達成したのである。
(議事要約 藤本隆宏)
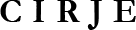

color.png)